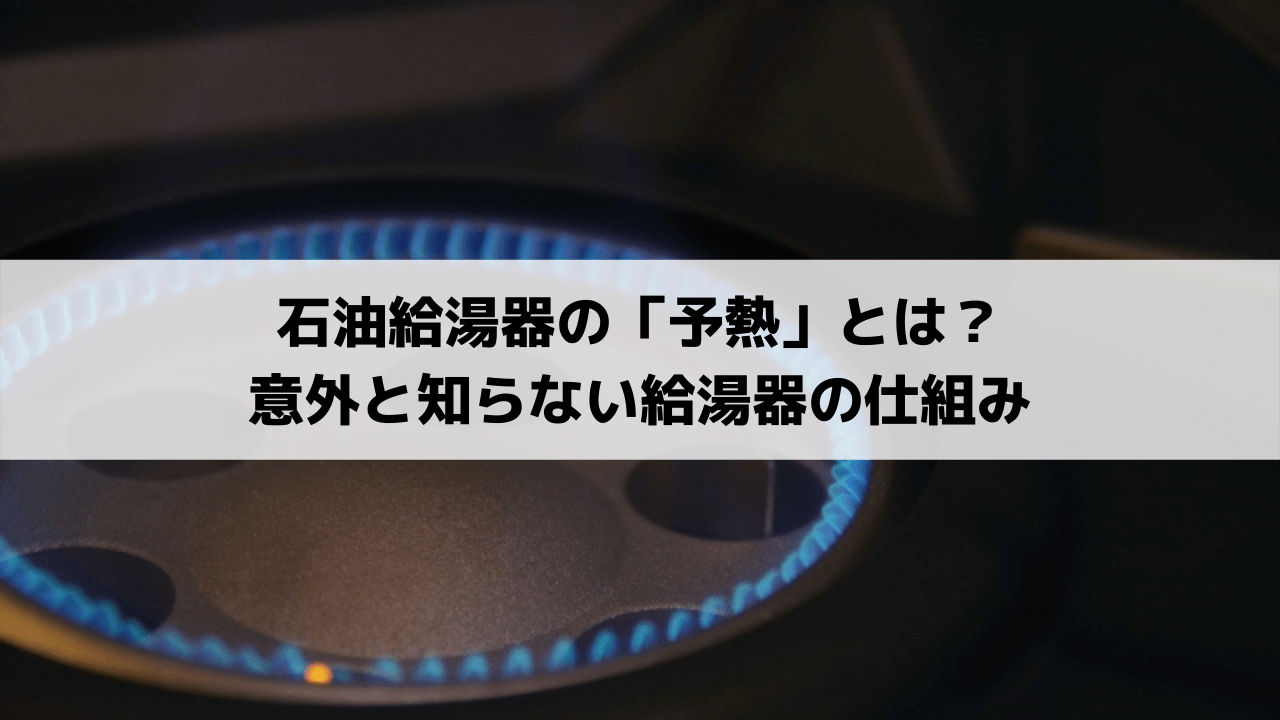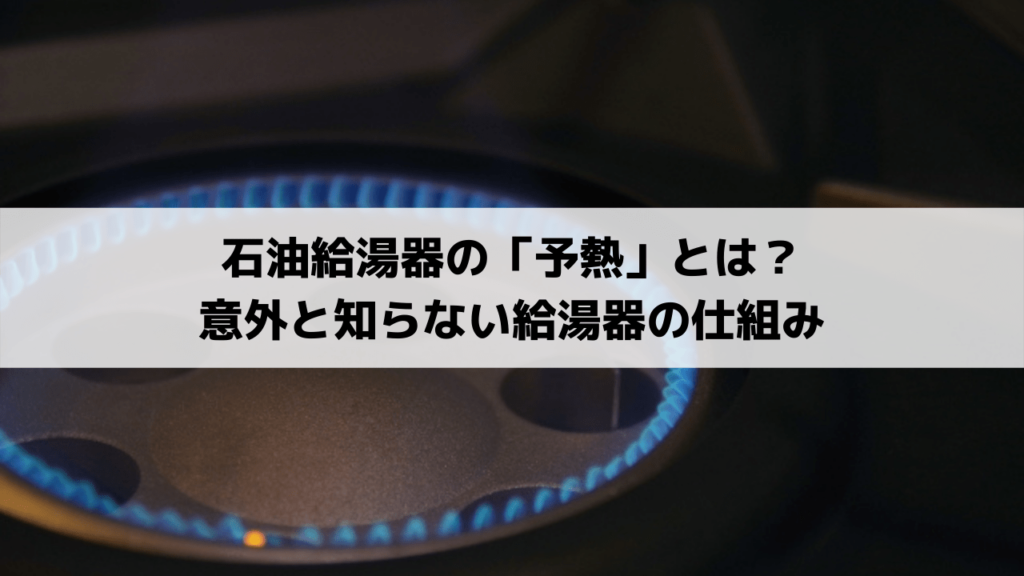
すずき設備社長の鈴木だ。
石油給湯器ユーザーの中には「予熱って何?」という人も少なくないのではないだろうか。これは壁掛けタイプの給湯器に見られる特徴で、しっかり理由のある動作の一つである。
毎回お湯が使えるようになるまで待たなければならない煩わしさがある一方で、実はメリットも享受していることを知っておいた方がいいだろう。そこで今回は「石油給湯器の予熱とは一体何なのか」について解説していく。
予熱=石油給湯器の壁掛けタイプ特有の機能

予熱作業とは、石油給湯器の壁掛けタイプにのみ搭載されている機能で、ガス給湯器や石油給湯器の置き型には搭載されていない。
石油給湯器の置き型はガンタイプバーナーと言って「灯油をそのまま噴射して火を付ける」という仕組みのバーナーだ。イメージ的には「アルコール度数の高い酒を口に含んで、ライターの火に向かってそれを吹き付ける」という感じである。
一方で壁掛けの石油給湯器の場合は気化式バーナーが搭載されていて、液体燃料である灯油をガス状にしてから燃焼させるという二段階になっている。そのためにバーナーに搭載されている気化器というパーツが予熱作業をして、灯油をガス状にさせるための準備運動をしているというイメージだ。
予熱をすることの特徴(メリット・デメリット)
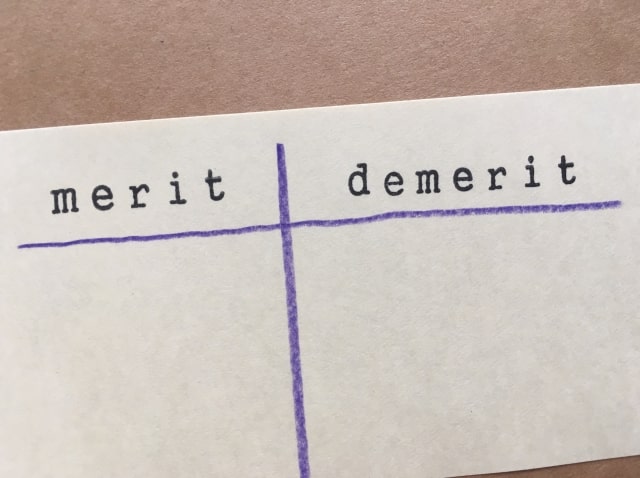
燃焼音が小さい
読者の多くは分からないかもしれないが、実はガス給湯器と石油給湯器は燃焼音の大きさが全然違う。石油給湯器の置き型、貯湯タイプの燃焼音に慣れていると、ガス給湯器や気化式バーナーを搭載している石油給湯器を使用したら「本当に燃えてる?」と感じるような音の小ささに感じるだろう。
理由として、まず灯油を汲み上げて噴射するポンプの大きさが全く違うということが挙げられる。石油給湯器の置き型の場合、ホームタンクから灯油を引っ張るパワーとバーナーに噴射するパワーが必要になるから、成人男性のこぶし大くらいの大きさの部品が使われている。
一方で壁掛けタイプの場合は、指3~4本くらいのサイズだ。汲み上げるのに必要なパワー、バーナーに灯油を送るのに必要なパワーが全く違うから、燃焼音の大きさは雲泥の差と言える。
もし「お風呂に入っている時に給湯器の音が気になる」とか、あるいは「夜遅くにお風呂に入る時に、近所迷惑にならないかどうか気になる」という場合は、同じ石油給湯器でも置き型から壁掛けタイプに変更するだけでも燃焼音の大きさはだいぶ変わるから、設置タイプの変更を検討してみてもいいかもしれないな。
ノズル詰まりが起きにくい
灯油を液体のまま燃焼させるのとガス状にしてから燃焼させるのとでは、ノズルの詰まりやすさに大きな違いが出る。石油給湯器の貯湯タイプは非常に頑丈な作りで、ちょっとやそっとじゃ故障しないくらいの丈夫さが魅力であるが、ノズルの詰まりだけはどうしようもない。
年数が経ってくると燃焼系エラー(特にE110とかE120)の原因になるノズル詰まりは、定期的にノズル掃除をしてやることで改善はされるが、そもそもノズル詰まりが滅多に起きない気化式バーナーであれば、このような症状に悩まされることはないだろう。
気化器が壊れやすい
前項ではノズルの詰まりがないということを挙げたから「気化式バーナーの方が優秀で故障が少ない」という印象を与えてしまったかもしれないが、実は気化式バーナーは壊れやすいという側面を持っている。
壊れやすいとは言っても、あくまで「経年劣化してきた時に壊れやすい」という意味であって、そんなに頻繁に壊れるものでは無い。しかし10年以上気化器が壊れずに使用できたというケースをほとんど見ないというのも事実だ。
そして厄介なのは「壊れてしまった気化器だけを交換する」ということが難しい構造になっており、気化器のエラーE370が出てしまった場合は、ほぼ例外なくバーナーごと交換ということになってしまうことだろう。

機種ごとに部品代は変わってくるとは言えバーナーは給湯器の主要部品の1つだから、ほぼすべての給湯器の中で1番か2番目に高価な部品になるんじゃないかと思う。
石油給湯器のエラーE370は気化器の異常|高額修理待ったなし
耐用年数に差し掛かっている給湯器がE370を出したら…

E370を出すとバーナーの交換になるケースが多く、その場合の修理費用は5万円を超えるケースが多いだろう。こうなってくると使用年数によっては修理するか買い替えるかを考えるのではないかと思う。
基本的に使用から7年を超えた給湯器でバーナーを交換するような修理が必要になった場合は、素直に新しい給湯器に交換した方が最終的にはお得になるのではないだろうか。
バーナー以外の部分の劣化具合にもよるが、E370も急に壊れたというよりは徐々に壊れていったことが予想されるし、その間の燃焼状態は良くなかったに違いない。そう考えると他の部品にも多少なり負担があったことが予想されるからだ。

修理に5万円以上かけるくらいなら、新しい給湯器を購入する資金に充てた方がいいと思うぞ。確かに修理をして長く使える可能性もあるにはあるが、逆にまったく使わないうちに別箇所の故障が出た時のことを考えたら悲惨だから、耐用年数に差し掛かってからの高額修理はあまりおすすめしない。
最後に
予熱と言うのは、灯油をガス状にさせて燃焼させるための準備運動と思ってほしい。これを知らないと「今すぐにお湯が使いたいのに1分~2分の予熱時間が鬱陶しい」と感じてしまうだろうが、これをすることで音が小さくなったり、燃焼効率が良くなっている部分もあるだろう。
弊社では同じ石油給湯器の中でも壁掛けタイプの給湯器をおすすめしているが、それは予熱と言う機能があって、それによって燃焼音が小さいなどのメリットはあるからだ。ぜひ、参考にしてくれ。